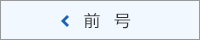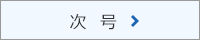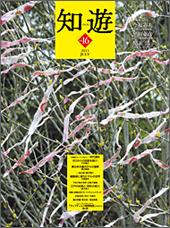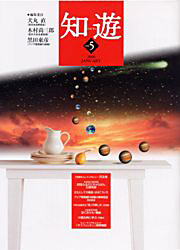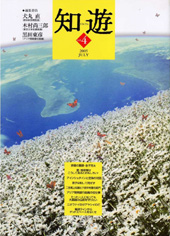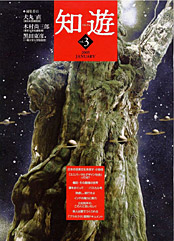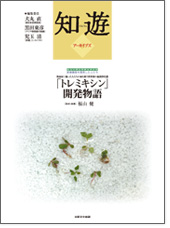知遊vol.23(2015年1月5日 発行)
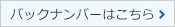
【知遊の人】
ムシって、本当に奥が深いんですよ
「自然」と「世間」の間で七〇余年
養老孟司(解剖学者、東京大学名誉教授)
【磯田道史の 古文書蔵出し話 お蔵入りの扉を開く】
「歴史のほんとう」を見つける旅
・甲賀忍者の里を訪ねて
磯田道史(歴史学者、作家、静岡文化芸術大学教授、本誌編集委員)
【特別寄稿】
オックスフォードで出会った経済学者たち
・モラルサイエンスの色彩が濃い英国流経済学を見直す
黒田東彦(日本銀行総裁、前本誌編集委員)
【動物行動学の視点】
負けて得する争い
・ヤドカリの世界を覗く
今福道夫(京都大学名誉教授、本誌編集委員)
【一枚の絵】
武者小路実篤、志賀直哉、柳宗悦ら白樺派の若き作家たちの夢が大原美術館に引き継がれた
・ポール・セザンヌ「風景」
柳沢秀行(大原美術館学芸課長)
【囲碁と読書は友だち】
碁会所がつくるコミュニケーション文化
・囲碁を通じて人の輪と和をつくる
マイケル・レドモンド(プロ棋士・日本棋院九段)
【仲代達矢の 無名塾へようこそ】
希林さんには、万事右へならえのご時世でも
「ここに我あり」っていうドーンとしたところがある
ゲスト 樹木希林(女優)
仲代達矢(俳優、無名塾主宰、本誌編集委員)
【日高敏隆最後のメッセージ】
世界を、こんなふうに見てごらん
日高敏隆(前京都大学名誉教授)
【ここが違う菌の常識】
麹の心は、和の心
・麹があれば、日本の未来は安泰
監修・青木 皐/文と絵・高田美果
【ヒューマンドキュメント・医療機器を開発した人たち】第23回
ワイヤレス医療機器の道を開いた
「生体情報モニタ」開発物語
福山 健(オルバヘルスケアホールディングス社外取締役)
特集記事
「知遊の人」は養老孟司さんをお招きしました。
養老さんは、東大医学部の解剖学者を経て、その実体験をもとに「脳」や「からだ」についてわかりやすい言葉で本を執筆されています。中でも、『バカの壁』は超ベストセラーとなり、書名は流行語にもなりました。
ユーモア溢れるインタビューをお楽しみください。
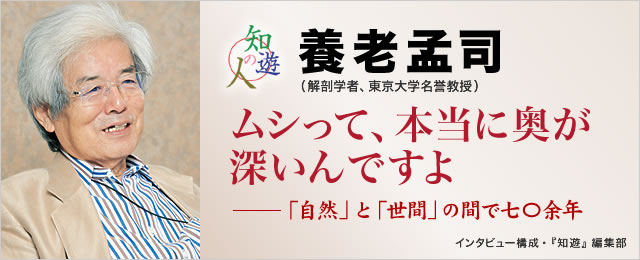
|
|
養老孟司(ようろうたけし)プロフィール
1937(昭和12)年神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学医学部を卒業後、解剖学教室に入る。東京大学大学院医学系研究科基礎医学専攻博士課程を修了。95 年東京大学医学部教授を退官。96 年から2003 年まで北里大学教授。東京大学名誉教授。89 年『からだの見方』でサントリー学芸賞、2003 年『バカの壁』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。『唯脳論』『涼しい脳味噌』『養老孟司の〈逆さメガネ〉』『運のつき』『死の壁』『超バカの壁』『自分の壁』など専門の解剖学、科学哲学から社会時評まで著書多数。
|
父との早い別れがトラウマになり、それが性格の根っことなったのかもしれない
――これまで「知遊の人」として21人の方にご登場いただきました。それぞれの道一筋に歩んでこられた方々に共通して感じるのは、ご両親や師に対する深い敬愛の念です。来し方を振り返っていただきながら、まず、お父様、お母様のことからお話しください。
1942(昭和17)年の晩秋、あと3日で5歳になるという日の夜明け前に、孟司少年は起こされた。結核を患っていた父のベッドを取り囲む大人たちの姿。頭の上のほうで誰かが「お父さんにサヨナラを」と促した。声も出せずに見つめている息子に「いいんだよ」と、父の文雄さんはほほえみかけ、まもなく息を引き取った。
90歳を過ぎても、現役の開業医として患者を診ていた母の静江さんは、生きることにも愛することにも「自分の思うまま」を貫き、そのために払う大きな代償にもめげず、生涯をまっとうした。その見事な生き方は、みずから執筆した著書『ひとりでは生きられない 紫のつゆくさ─ある女医の95年』(かまくら春秋社発行)に詳しい。その著書のなかで、文雄さんは静江さんに笑顔を見せながら、「僕は良い人間だから早く逝く。君はわがままな人間だから、なかなか死ぬことはできないよ。それを『業』というんだ。立派な仕事を持っているし、君なら大丈夫だと信じている。子供たちを頼むよ」(著書の文字遣いのママ)という言葉を残して世を去った、とある。
――愛すべきところの多いかわいい方だったようですね、お父様から見れば。お父様は人間的に大人で、落ち着いたお人柄だったとか。
 34歳で世を去った文雄さんから「君なら大丈夫」と信頼され、子供を託された静江さんは、鎌倉市で開業医として大車輪で働き、3人の子を育てた。 34歳で世を去った文雄さんから「君なら大丈夫」と信頼され、子供を託された静江さんは、鎌倉市で開業医として大車輪で働き、3人の子を育てた。
人間性豊かな師にめぐり合えた東大解剖学教室
――東大の医学部を卒業なさって解剖学の研究室にお入りになったんですね。
解剖学教室には、もう一人、中井先生と同期生である細川宏教授がいた。細川教授は、養老さんが解剖学教室に入ったときの歓迎会で「自分は、中井先生と同じく終戦の年に卒業した。戦後になって専攻を選ぶとき、医学のなかでいちばん確実な学問はなんだろうか、と考えた。結論としてそれは、古くからある解剖学だと思った。だから私は解剖学を選んだのだ」と語った。その言葉は、若い養老さんの腑に落ちた。よき師を得て、地道にひたすら死体に向かう日々が始まった。
細川先生は病床で詩やエッセイを書きつづった。透徹した目で自分の病に向き合い、見舞いに届けられた花々を、ユーモアを交えてスケッチした詩や文章が遺された。亡くなって10年後、中井先生は、2人の師である小川鼎三名誉教授とともに編者となり、1冊の本を上梓した。『詩集 病者・花 細川宏遺稿詩集』(現代社発行)は、医学にかかわるすべての人々、医師や看護師必読の書と語り伝えられ、いまなお読み継がれている。
養老さんが2人の師について話すとき、「小さいころご両親を亡くされた」中井先生にはみずからの幼児体験を、惜しまれつつ早逝した細川先生には父・文雄さんの姿を重ねているのではなかろうか、と、その淡々とした語り口から感じる。
|
|
 |
|
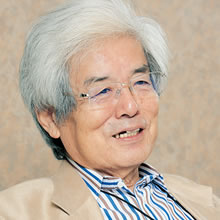

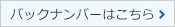
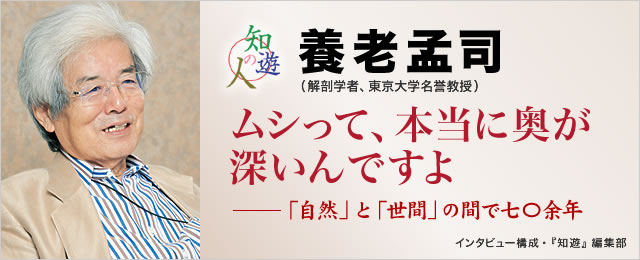
 34歳で世を去った文雄さんから「君なら大丈夫」と信頼され、子供を託された静江さんは、鎌倉市で開業医として大車輪で働き、3人の子を育てた。
34歳で世を去った文雄さんから「君なら大丈夫」と信頼され、子供を託された静江さんは、鎌倉市で開業医として大車輪で働き、3人の子を育てた。