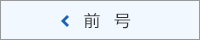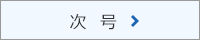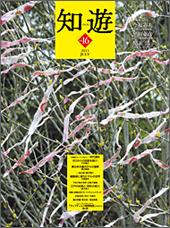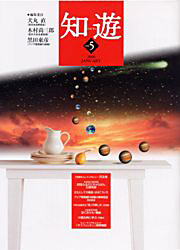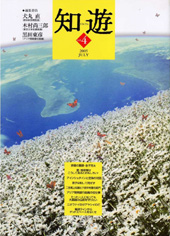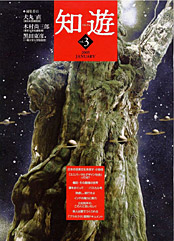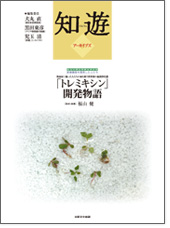知遊vol.24(2015年7月5日 発行)
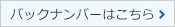
【知遊の人】
「インタレスト」がわたしの原点です
好奇心と想像力いっぱいの八九歳
安野光雅(画家、絵本作家)
【一枚の絵】
ロダンの三作品が勢ぞろいした背景
・白樺派の熱狂がそこにあった
柳沢秀行(大原美術館学芸課長)
【磯田道史の 古文書蔵出し話 お蔵入りの扉を開く】
「もし……ならば」と考える反実仮想に学ぶ
・教科書型秀才の判断力貧困時代に
磯田道史(歴史学者、作家、静岡文化芸術大学教授、本誌編集委員)
【囲碁と読書は友だち】
呉清源先生の恐るべき集中力と天賦の才
・牛栄子、一五歳の最年少女流棋士誕生を祝う
マイケル・レドモンド(プロ棋士・日本棋院九段)
【動物行動学の視点】
次世代を担う「子供」について考える
・彼らが、未来をつくる
今福道夫(動物行動学者、京都大学名誉教授、本誌編集委員)
【名著探訪】
耕す文化の時代
・セカンド・ルネサンスの道
木村尚三郎(前東京大学名誉教授、前本誌編集委員 2006年逝去)
【仲代達矢の 無名塾へようこそ】
芝居はもう一つの現実を見せるもの
そこに嘘がないから感動できる
ゲスト 萩本欽一(コメディアン)
仲代達矢(俳優、無名塾主宰、本誌編集委員)
【ヒューマンドキュメント・医療機器を開発した人たち】第24回
医療機器産業への参入を成功させる
医工連携「製販ドリブンモデル」開発物語
福山 健(オルバヘルスケアホールディングス社外取締役)
特集記事
安野さんは、島根県津和野町出身の画家・絵本作家です。その豊かな好奇心、想像力をもとにつぎつぎと作品を発表し、国際アンデルセン賞、紫綬褒章を受賞するなど、国際的に高い評価を得ています。
89歳にしてなお好奇心と想像力に溢れる安野さんに、お話を伺いました。
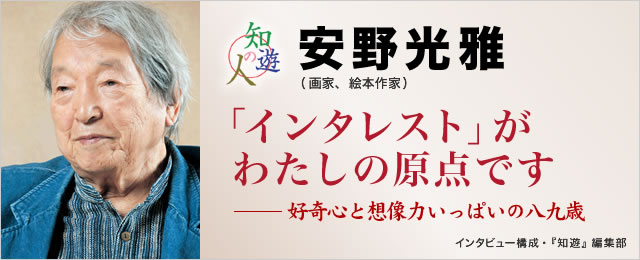
|
|
安野光雅(あんのみつまさ)プロフィール
1926(大正15)年島根県津和野町生まれ。山口師範学校研究科修了。小学校の美術教員を経て、画家になる。1968年、文章のない絵本『ふしぎなえ』(福音館書店)が初めての絵本。豊かな好奇心、想像力をもとに独創的な作品をつぎつぎに発表。その多くが海外のさまざまな国で紹介され、高い評価を得ている。科学・数学・文学などにも造詣が深く、絵本以外の作品も多数。2010年には、森鴎外訳『即興詩人』を口語訳した『口語訳 即興詩人』を上梓。
多くの業績に対し、ブルックリン美術館賞(アメリカ)、ケイト・グリナウェイ賞特別賞(イギリス)、最も美しい50冊の本賞(アメリカ)、BIB 金のリンゴ賞(チェコスロバキア)、国際アンデルセン賞、紫綬褒章、菊池寛賞などを受賞。2012年、文化功労者。
主な著作に『ABCの本』『あいうえおの本』『旅の絵本』『天動説の絵本』『はじめてであうすうがくの絵本』(福音館書店)、『わが友・石頭計算機』(ダイヤモンド社)、『算私語録』『絵のまよい道』『繪本 三國志』(朝日新聞出版)、『安野光雅の画集 Anno 1968-1977』『繪本 平家物語』『繪本 シェイクスピア劇場』(講談社)、『安野光雅・文集(全六巻)』(筑摩書房)、『昔の子どもたち』『明日香村』(日本放送協会出版)、『絵の教室』(中央公論新社)、『原風景のなかへ』『少年時代』(山川出版社)などがある。
|
津和野小学校時代の心やさしい少年ミッちゃん
――お書きになった『絵のある自伝』(文藝春秋刊)にある「つえ子のこと」というエピソードを読むと、小学生のころの安野先生はとても心やさしい少年だったのだなあと感動します。
つえ子ちゃんは、明るい子だったという。いつもよく笑い、泣いたり卑屈になったりすることのない子だった。隣りの席の「ミッちゃん」こと安野光雅少年は、なにをしてあげることもできず、おどけてつえ子ちゃんを笑わせるのがせいいっぱいだった。
60年ぶりのつえ子さんは、安野さんのことをよく覚えていた。子どものころの面影はなかったが、明るさは変わらなかった。農家に嫁ぎ、農作業をしながら4人の息子を育て、4人とも大学を卒業させた、という。いま悩んでいるのは、畑を荒らすイノシシやサルに手を焼くことくらいだ、と屈託のない笑顔を見せたそうである。
 大好きな絵を描き続けながら、津和野小学校を卒業後、宇部工業、山口師範などで学び、安野さんは山口県徳山市の小学校で教師となる。 大好きな絵を描き続けながら、津和野小学校を卒業後、宇部工業、山口師範などで学び、安野さんは山口県徳山市の小学校で教師となる。
安野さんも胸を熱くしてその講演を聴いた。その日の慰労会の席で、小原さんはどこかで安野さんの絵を見て「この人を玉川学園の美術教師に招きたい」といわれたらしい。一種のスカウトであろうか。その言葉をじかに聞いた安野さんの勤め先の校長が、「後のことはなんとでもするから、この機会に東京へ行ったらどうか」と、熱心にすすめてくれた。
思い切って上京し玉川学園に行くと、小原さんは忙しいらしくなかなか面会できない。2日間続けて応接間で待つ若い青年を見て、「マタ、ヤッタカ」と憐れんで、昼食をごちそうしてくれた教授があった。どうやら、あのスカウトは酒席でのスタンドプレイだったか、と安野さんは笑顔でいう。その教授の計らいで、小原さんに会うことはできたが、学校側の都合で、安野さんは玉川学園の出版部で編集の仕事に携わることになった。
結婚し、東京都の公立小学校に勤務 父となり、やがて画業一筋に
――東京都の教員試験にパスされて、三鷹市や武蔵野市の小学校に勤務なさったのですね。そして、26歳でミドリ夫人と結婚なさいます。
昭和30年に長男雅一郎さん誕生、4年後に長女正子(せいこ)さんが生まれる。そのころから出版社の装丁の仕事が増え、教職との両立がむずかしくなったので教師を辞め、画業一筋の生活をすることになった。2人のお子さんを育てた経験のなかで、いかにも若い父親らしいと感じたエピソードを2つ紹介したい。
1つは雅一郎さんの4歳くらいのときのこと。安野さんと、安野さんのお母さんがちょっとした口論をしていたら、雅一郎さんが「おばあちゃんも好きだよー、お父ちゃんも好きだよー」といって泣き出した。その涙に、いたく反省し、以来家族と喧嘩はしていない。
もう1つは、正子さんのエピソード。安野さんが仕事に疲れて指圧師に来てもらったときのこと。
肩や腰を強く圧してもらい、その痛みに耐えていると、3歳くらいだった正子ちゃんは父親がいじめられているとでも思ったのだろう、物差しを持ってきて指圧師をぶとうとした。慌てて正子ちゃんを引き離したそうだが、子育てをした人にはこれに似た経験が少なからずあると思う。
「4歳くらいまでの子どものありようは、そこを支点として、その後の子どもがするであろうあらゆることと釣り合いが取れている、というが、本当にそうだと思う」と、安野さんはいう。そして、「子どもたちがしてくれたことに、一生をかけて報いたい」と、若い父親であった日に、思いを新たにした姿には、さらに遠い日、同級生のつえ子ちゃんを笑顔にしようとおどけて見せた子どものころのミッちゃんが重なってくる。
|
|
 |
|


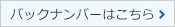
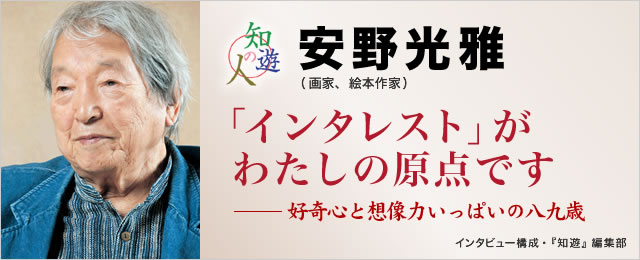
 大好きな絵を描き続けながら、津和野小学校を卒業後、宇部工業、山口師範などで学び、安野さんは山口県徳山市の小学校で教師となる。
大好きな絵を描き続けながら、津和野小学校を卒業後、宇部工業、山口師範などで学び、安野さんは山口県徳山市の小学校で教師となる。